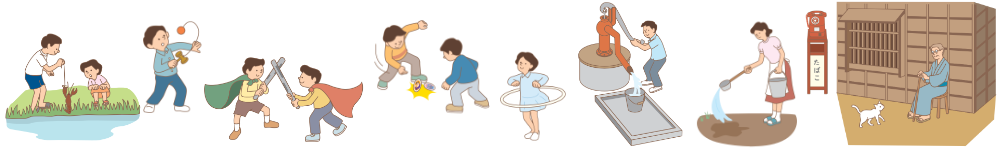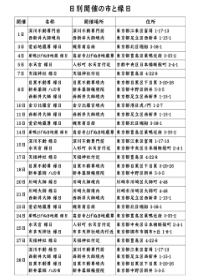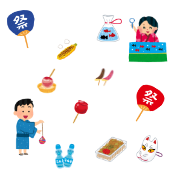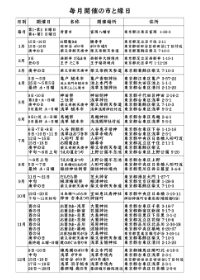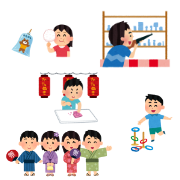昭和の縁日 技 「ゴリラ風船」
諏訪神社の鳥居を抜け、日暮里駅へ向かって少し歩いた左側にある養福寺の入り口を入った場所が、毎年の定位置で繰り広げられる舞台です。
 道から少しへこみ養福寺さんの入り口で、小さな広場になっているので混んでも道を塞ぐことはありません。見た目の人相は怖いくらい悪く体もでかい、それにとにかく口が悪い。
道から少しへこみ養福寺さんの入り口で、小さな広場になっているので混んでも道を塞ぐことはありません。見た目の人相は怖いくらい悪く体もでかい、それにとにかく口が悪い。
なのに憎めない、立て板に水のような切れのいい喋り。怒る客は誰ひとりいない不思議な雰囲気。どんなに注文が入っても、丁寧に同じことを唱えながら風船を膨らませていく、決して手を抜かない仕事。
一つ作るのに大体五分はかかる、そのたびに例のごとくお経のような口上を唱える幾つかのパターンがあり。それにアドリブのようなものも入れての熱演だから、人の絶えることのない人気者だった。
もう一つ目を引いていたのがパリでの興行写真。これもよく自慢していた。エッフェル塔を背景に興行している写真でした。 「香具師の俺が、本当にフランスから招待されたんだ」と言っていました。昭和30年代、外国に行くなど一般ではまずありえない時代に、ゴリラ風船の興行で招待されたというのは、本当にすごいことだと今も感じています。
後に、テレビにも出演したと写真が増えていたのを覚えています。いつも来るたびに掲げている、屋号のゴリラ商会と書かれた看板と、ベニヤで出来ている掲示板のような物も商売道具。ここに色々な写真が貼り付けてあり、この場所が来るたびに増えていっていたのです。
縁日の昼、所定の場所へ商売道具を並べるのは必ず奥さん、その脇で一升瓶を抱えて、へべれけになるまで飲んでいるのは当の本人。この光景は長い年月変わりません。そして昼寝、他の店は商売を始めているのに平気です。
この方の容姿を表現すると身の丈6尺(180cm)、体重25貫(90Kg)顔は黒く日焼けし、鬼のような感じです。
一瞬、近寄りがたい感じなのですが本当はとてもやさしく子供が好きで、夕方目がさめるころになるとやっと本業の支度をします。支度と言ってもタオルで頭に鉢巻をするだけ、皆もこのことを良く知っていてこのころになると、どことなく人垣が出来ているのです。
ところが足元はまだ定まらずフラフラしながら足踏みのポンプを用意、まず細長い風船を膨らませます。たこの鉢巻に使用する為の副材です。この用意ができるころには、すごい人垣になっています。
これからが口上売の始まりで、お客さんとの掛け合い。悪口ばかり浴びせまるで漫才、そしてメインの風船をおもむろに膨らませる。このときに得意の「お経」を唱える、それもすごい形相で、このころにはお客さんも皆完全に「ゴリラ商会」のおじさんに飲み込まれている。
誰ともなく一つくれと声がかかると、後は連鎖で飛ぶように売れる。ところが、作るのが間に合わない。怒り出す、酒を飲む。これの繰り返しなのに、誰も文句を言わず待っている。
何か不思議な光景でした。客の心をつかむ商売の原点です。
物を作る、言葉を作る、想い出も作ってくれた「ゴリラ商会」でした。
後、弟さんも参加されていたのですが看板役者のお兄さんが亡くなり、その後はほとんど見ることが出来なくなってしまいました。
某落語家(・・・三太夫)さんを見ると、売りとしている仕草がとても似てて、いつも思い出してしまいます。